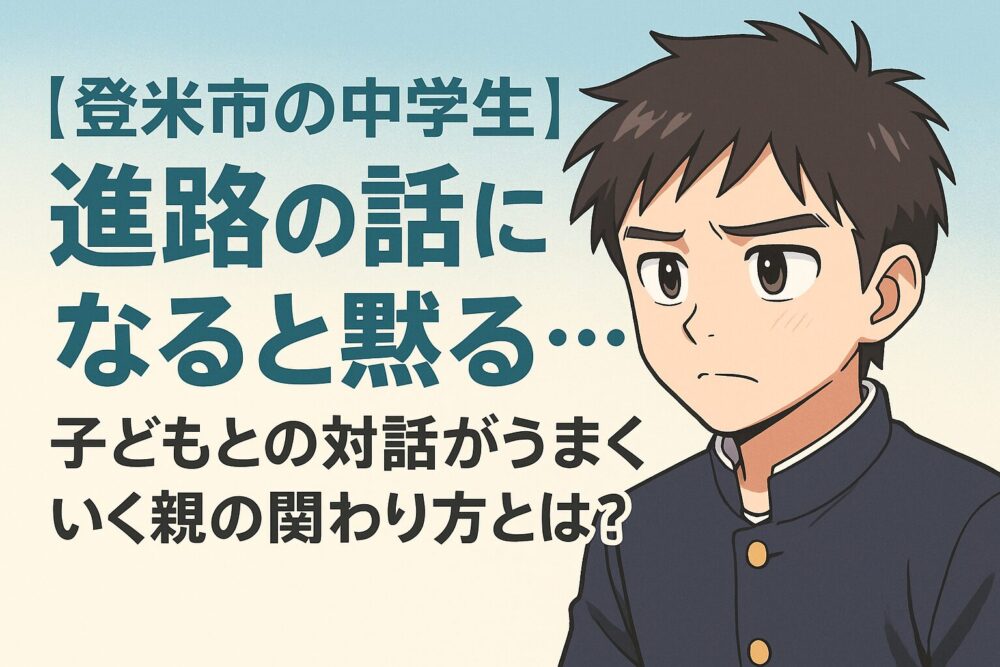進路の話を避ける子どもたちと、戸惑う保護者へ
「ねぇ、将来どうしたいの?」「高校、どこ受けたいの?」
そう尋ねると、子どもが黙ってしまう。返事が返ってこない。あるいは「わかんない」と一言だけ。
登米市の保護者の方々とお話ししていると、こうした声をよく耳にします。
子どもを思うからこその問いかけが、なぜか壁になってしまう。
今回はその理由と、対話のヒントを一緒に考えてみたいと思います。
なぜ中学生は進路の話になると黙るのか?—登米市の子どもたちの特徴から考える
中学生が進路の話になると黙ってしまうのは、怠けているからでも、無関心だからでもありません。
むしろ「自分なりに悩んでいるからこそ、言葉にできない」ということが多いのです。
特に登米市の子どもたちは、都会に比べて環境が穏やかで、競争が少ない分「急いで決める必要を感じていない」傾向があります。
また、「周りと同じでいたい」「失敗したくない」という気持ちが強いため、はっきりした目標がないまま、話題を避けてしまうのです。
「なんで何も言わないの?」が逆効果な理由—親の気持ちと子どもの本音のズレ
保護者が「何も考えてないの?」と聞いてしまうのは、心配の裏返しです。
でも、子どもからすれば「どうせ何言っても否定される」「親の望む答えを言わなきゃいけない」と感じてしまうこともあります。
特に中学2〜3年生は、自己肯定感が揺れやすい時期です。
「自分の考えを言っても大丈夫だ」と思える安心感がなければ、本音を出すのは難しい年頃です。
登米市内の高校選びの現実と、情報格差の壁
登米市周辺の中学生にとって、進路選びは「地元で決めるか」「遠方も視野に入れるか」という選択肢が現実的に出てきます。
しかし、情報量が限られている家庭も多く、「佐沼高校に行ければいいよね」「迫桜はどうなの?」といった曖昧な会話で終わってしまうことも少なくありません。
子ども自身も「どこが自分に合ってるのか、どうやって調べたらいいのか」がわからず、不安を口にできずにいることが多いのです。
だからこそ、保護者も「一緒に情報を集めてみようか」というスタンスで関わることが、信頼と安心を生みます。
子どもが話してくれる親の共通点—言ってはいけない言葉・言ってよかった言葉
子どもが進路の話をしてくれる親には、ある共通点があります。
それは「評価や指導ではなく、共感を先に出す」ということです。
たとえば、
❌「そんなレベルじゃ無理だよ」
❌「もっと現実を見なさい」
ではなく、
✅「そう思った理由を教えてくれる?」
✅「もし叶うなら、どんな高校生活をしてみたい?」
といった問いかけは、子どもが安心して言葉を出せるきっかけになります。
まずは進路ではなく“日常”から—会話のきっかけを育てる習慣
進路の話をする前に大切なのは、普段の会話です。
「今日の部活どうだった?」「最近、どの教科が好き?」といった日常の中に、信頼関係は育まれていきます。
子どもは「聞かれてる内容」だけでなく、「どういう気持ちで聞かれているか」を敏感に感じ取ります。
焦って詰めるように話すよりも、何気ない会話の中で「あなたの考えを大切にしてるよ」と伝えることが、対話の土台をつくっていきます。
おわりに:一方的に導くのではなく「一緒に考える」親子関係へ
進路は人生の大きな選択ですが、すべてをこの中学時代に決めきる必要はありません。
大切なのは「自分で考え、自分の道を選べるようになる力」を育てていくことです。
そのために、保護者ができることは「急かさず、焦らず、隣で歩くこと」。
「この子は、まだ黙ってるけど、ちゃんと考えているんだ」と信じて関わることが、なによりの支えになります。