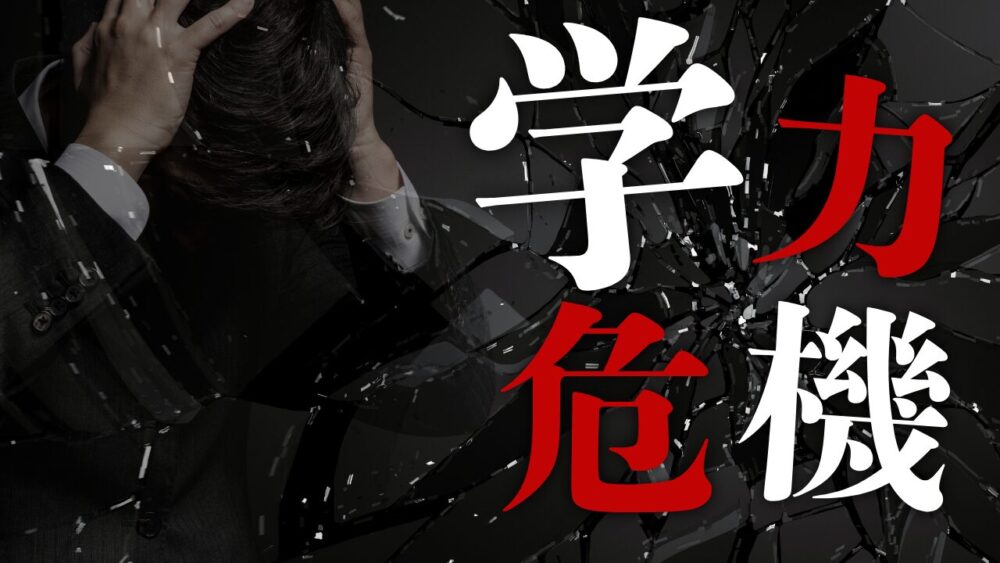登米市内で行われた実力テストの結果が示す衝撃の数字
2025年、登米市内で実施された実力テストの結果は、教育関係者や保護者に大きな衝撃を与えました。
5教科の平均点が、基準とされる水準よりもおよそ50点も下回っていたのです。
この「50点下回る」という数字は、単なる一つのテスト結果にすぎないと片づけられるでしょうか。答えは否です。これは、登米市全体として学力の基盤が大きく崩れつつあることを示す、深刻なサインにほかなりません。
平均点が50点以下ということは、半分以上の問題が「わからなかった」ということです。これが一部の生徒の結果ならまだ理解できます。しかし、5教科全体で同様の傾向が見られるとなれば、単なる偶然ではなく、構造的な問題と考えるべきです。
学力差が広がる中学生の教室の現実
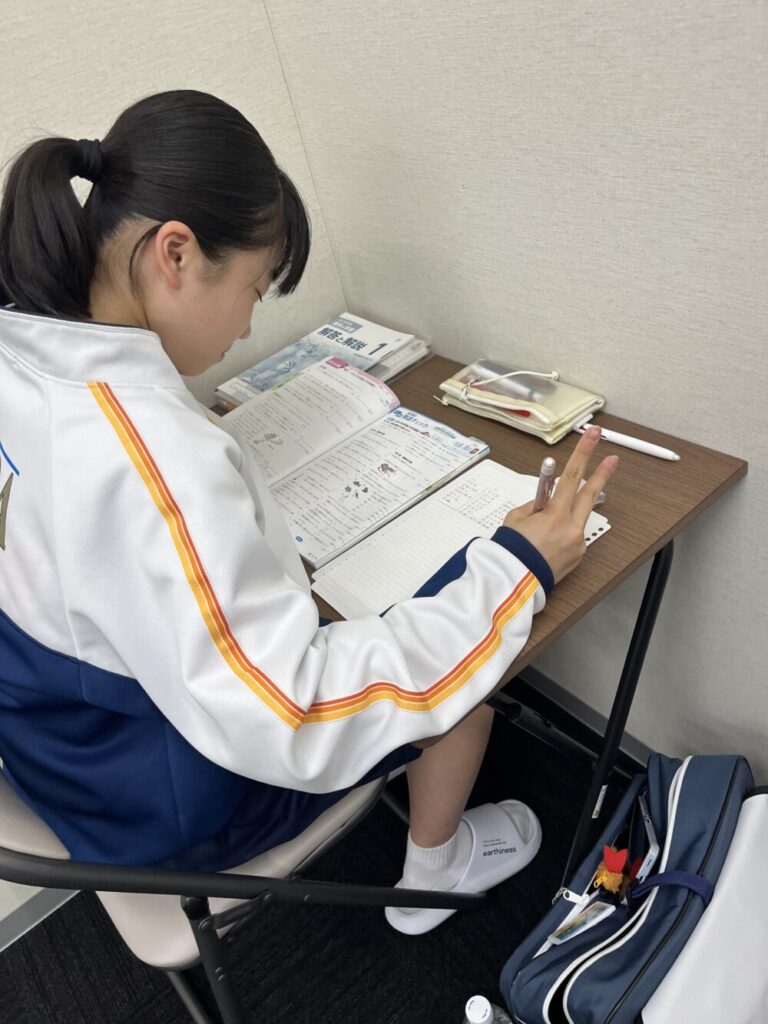
テストの内訳を見ていくと、さらに深刻な実態が見えてきます。
上位層の生徒は安定して高得点を取っている一方で、下位層の生徒は基礎が定着しておらず、ほとんど点数を稼げません。その差は50点以上。
同じ教室で学んでいても、
- 「簡単すぎる」と感じる生徒
- 「問題文の意味すら理解できない」と感じる生徒
が同居しているのです。
たとえるなら、マラソン大会で同じスタートラインに立っているのに、すでに半数は靴すら履いていない状態。先生が「さあ走ろう!」と声をかけても、全員を同じゴールへ導くのはほぼ不可能です。
学力差の拡大は全国的な傾向ではありますが、登米市では特にその幅が大きく、学校現場の先生方も「授業の設計が難しい」と頭を抱えています。
小学校から始まる基礎の抜け
学力低下の原因は中学校から突然始まるわけではありません。実際には、すでに小学校の段階で基礎が抜け落ちているのです。
ある小学6年生の事例があります。
「算数が苦手」と言って塾にやってきました。確認すると、驚くべきことに「くり下がりの引き算」が理解できていませんでした。本来なら低学年で習得している内容です。
この段階でつまずいたまま進級すると、分数、小数、割合といった単元は当然理解できません。授業が先へ進むたびに「何がわからないのかもわからない」状態に陥り、結果としてテストでは半分以上を落とすことになります。
こうした「基礎の抜け」は珍しくなく、むしろ見えにくいために深刻です。子ども本人も「自分がどこでつまずいているのか」を認識できないまま、学年を積み重ねてしまうのです。
学校現場の声 両極端な学力

知り合いの先生方と話をする機会がありました。そこで語られたのは、登米市の学校現場が直面している厳しい実情です。
「中学校の授業は小学校の内容を理解している前提で進めるが、実際には理解できている生徒は半分以下。」
例えば中学1年の数学なら、分数の計算ができていることが前提です。しかし実際には、掛け算や割り算から怪しい生徒もいるのです。その一方で、小学生の段階から応用問題をスラスラ解ける生徒もいます。
つまり、学力の差は年々広がり、両極端に分かれてきているのです。先生方は「集団授業で全員を同じペースに引き上げるのはほとんど不可能だ」と口を揃えます。
学習習慣の欠如とスマホ依存
さらに問題を複雑にしているのが学習習慣の欠如です。
多くの先生が「正直、家ではほとんど勉強していない」と口にします。
放課後はスマホやゲームに時間を奪われ、気づけば数時間。夜更かしをして睡眠不足になり、学校では集中力が続かない。授業が理解できないからますます勉強しなくなる。この悪循環はもはや典型的です。
よくあるのが次のようなやり取りです。
「勉強してるの?」
「やってるよ!」
「何分?」
「30分はやってる」
一見すれば真面目に取り組んでいるように見えます。
しかし実態は、スマホに8時間、勉強は30分。その30分でさえ、親からの質問をかわすための“防衛策”であることも少なくありません。
学習習慣の欠如は、単なる「怠け」ではなく、時間の使い方が歪んでいることに起因しています。
可処分時間の乱れ
ここで注目すべき概念が「可処分時間」です。
※可処分時間:学校や部活動、習い事を除いて子どもが自由に使える時間。
この時間の使い方が学力に直結します。
例えば、同じ「勉強」でも、
- 1時間スマホ+30分勉強
と - 8時間スマホ+30分勉強
では、効果に雲泥の差があります。後者は「勉強した」と言っても、実際には学びが生活の中でごくわずかな割合しか占めていません。
つまり、学力低下の背景には可処分時間の乱れが大きく影響しているのです。
小さな成功体験からの再生
冒頭の小学6年生も、基礎からやり直すことで変化が訪れました。
最初は「こんな簡単な問題からやるの?」と不満を口にしました。
しかし、解けるようになると「できた!」という感覚が自信につながりました。
その積み重ねが学習意欲を呼び覚まし、次第に学校の授業についていけるように。今では「学校が楽しい」と言えるようになりました。
学力の回復は決して一足飛びにはいきません。小さな成功体験の積み重ねこそが、学びを好循環に変える唯一の道なのです。
実力テストの平均点が50点下回るという意味
5教科の平均点が基準より50点も下回るという現実は、登米市の子どもたちが学力の土台を大きく失いつつあることを意味します。
- 小学校からの基礎の抜け
- 学力差の両極化
- 学習習慣の欠如
- 可処分時間の乱れ
- 睡眠不足と集中力の低下
これらの要因が複雑に絡み合い、学力を大きく引き下げているのです。
登米市として直視すべき課題
この状況を子ども一人や学校だけで解決するのは困難です。
家庭、学校、地域が一体となり、
- 小学校段階での基礎の確認
- 可処分時間の健全な使い方
- 学習習慣を身につける環境づくり
を徹底することが求められます。
まずは「5教科の平均点が50点下回っている」という現実を直視し、危機感を共有すること。それが出発点になります。
登米市内の小学生・中学生に対し大人がすべきことは?
登米市が直面している「5教科で平均点が50点下回る」という結果は、決して軽く受け止められるものではありません。
このままでは、子どもたちの未来だけでなく、地域全体の将来にも暗い影を落とします。
私たち大人が果たすべき役割は明確です。
「学力低下の芽を早期に見逃さない」姿勢を持つこと。
だからと言って塾だ!家庭教師だ!ではなく、まずは家庭でできることを子供と向き合いともに考える。
そして基礎を確かめ、学習習慣を育て、可処分時間を意識することです。
登米市は必ず変わると思います。
この取り組みを、家庭・学校・地域が一体となって進めることが、登米市の未来を守るための具体的な一歩となるのではないでしょうか。