ちゃんと勉強しているのに成績が上がらないのはなぜ?

「ちゃんと勉強してのに、なかなか成績が上がらないんです…」



どうしてうちの子供はちゃんと勉強しているのに上がらないんだろう?



ほほう。どうやら成績のことでお悩みのようじゃな。



授業はちゃんと受けています。ノートも取っています。でも成績が。。。どうしたら成績が上がるんですか。



それでは本日は自立学習についてお話をしよう。
授業を受けること自体は大切です。わからないことを教わるのは、学力アップの第一歩。でも実は、「教えてもらうこと」だけでは、成績は思うように伸びません。
その理由は
成績アップには“自立した学習”が欠かせないからです。
この記事では、「どうして教わるだけではダメなのか?」という疑問を解き明かしながら、“自分で考え、自分で進める学習法”の重要性についてお伝えします。
「勉強しているのに成果が出ない…」そんな悩みを抱えるお子さまや保護者の方に、きっとヒントになるはずです。
自立学習の重要性「教えてもらうだけ」では成績は伸びない
勉強が苦手な子にとって、わかりやすく教えてくれる先生の存在はとてもありがたいものです。
授業中は「なるほど!」と感じる場面も多く、「今日はよく理解できた」と安心することもあるでしょう。
でも――
その“わかったつもり”が落とし穴になることもあります。
成績を上げるために本当に必要なのは、「その内容を自分の力で解けるようになること」です。
授業中にわかった気になっても、自分で問題を解こうとしたときに手が止まってしまう。これは、“教えてもらった”だけで、“自分で使えるようにする練習”が足りていないサインです。
特に中学生・高校生になると、自分の頭で考え、解く力が問われる問題が増えてきます。
つまり、「自立学習」ができなければ、どんなに良い授業を受けても、成績は思うように伸びません。
ここからは、なぜ“自分で学ぶ力”が必要なのか、そして自立学習を身につけるためにどうすれば良いのかを、詳しくご紹介していきます。
登米市の生徒は自立した学習ができていない?
登米市の中学生と日々向き合っていると、「自立した学習」ができていない生徒の多さに、正直なところ危機感を覚えることがあります。
わからない問題があればすぐに「学校の先生がちゃんと教えてくれなかった」と責任を外に向け、自分で調べようとする姿勢がほとんど見られない。
少しでも応用的な問題が出されると「これは習ってないから無理」と、最初から考えることすら放棄してしまう。そんな様子に何度も直面してきました。
また、授業中に先生が黒板に書いた内容をただノートに写して満足している生徒や、国語の勉強といえば“漢字練習だけ”という子も少なくありません。
定期テストに向けてワークをやるように伝えても、本気で取りかかるのはテスト直前、2日前や前日というケースも珍しくないのです。
そして口をそろえて言います。
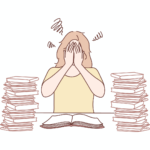
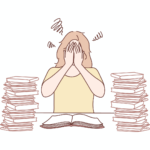
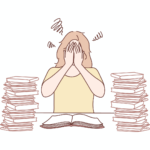
ひえ~~~勉強しているのに成績があがらない。
もちろん、これは登米市に限った話ではありません。
ただ、地方ならではの「競争の少なさ」「周囲に流されやすい雰囲気」「学習への危機感の薄さ」が、この“指示待ち”の姿勢を強くしてしまっているように感じます。
こうした現状を打開するには、ただ「勉強しなさい」と言うだけでは不十分です。
必要なのは、“自分で考え、動く力”を育てること。つまり、本当の意味での自立学習の支援です。
自立学習とは、放任することではありません。
生徒が「自分で決めて動く経験」を積み重ね、少しずつ自信をつけていくように、大人が仕組みや声かけで支えていくことです。
テストや受験のためだけではなく、生きる力としての学びを育てる。
登米市の教育の未来を考えるうえで、今まさに求められている視点だと感じています。
登米市の生徒におすすめの自立学習とは?
登米市の多くの中学生・高校生を見ていて感じるのは、
「自分のペースで学べる時間が意外と少ない」ということです。
部活動が遅くまである生徒が多く、学校が終わって家に着くのは19時過ぎというケースもよくあります。
そこから夜の練習スタート。
土日は大会が入り学習時間は取れない毎日。
そんな中で、ただ授業を受けるだけでは、理解を深めるための“自分で手を動かす時間”が足りなくなってしまいます。
では、登米市の生徒にとって効果的な自立学習とはどのようなものでしょうか?
ポイント①:自分専用の「今日やることリスト」を作る
限られた時間で効率よく学ぶには、その日の学習内容をあらかじめ決めておくことが重要です。
「今日は英語の不規則動詞を10個覚える」「数学のワークを2ページ解く」といった具体的な目標設定が、自分の学習の道しるべになります。
ポイント②:スマホや誘惑を断つ「集中環境」を整える
登米市は自然が豊かで静かな場所も多く、自宅学習には最適な環境があります。
ですが、スマホやテレビといった誘惑があると、せっかくの静けさも台無しに。塾や図書館を“集中場所”として活用するのも有効です。
ポイント③:わからない問題は“あとで質問する”癖をつける
自立学習は「全部自分でやる」ことではありません。
むしろ、「自分でやってみてわからなかったところを質問する」ことが本当の自立です。
塾で先生に質問できる時間を“最大限に活かす”ためにも、事前に自分で挑戦する姿勢が大切です
自立学習は、“最初から一人でできる”ものではないということです。
登米市の生徒の自立学習が成功するためには「サポート」が必要不可欠?
「自立学習」と聞くと、「じゃあ、もう全部自分でやらせるべき?」と思われるかもしれません。
でも実際は、一人きりで頑張らせることが自立ではありません。
むしろ、自立学習がうまくいくためには
“一緒に伴走してくれる存在”が必要不可欠なのです。
たとえば、生徒が「どこから手をつければいいのか分からない」と悩んでいるとき。
「じゃあ、まず今週の目標を一緒に決めてみようか」と声をかけるだけで、その子は一歩を踏み出せます。
■ 自立学習を支える“寄り添い型サポート”
- 学習計画は「一緒に」立てる
→ 生徒の意見や希望を聞きながら、「無理なく続けられる学習スケジュール」を共に作っていきます。 - 進み具合を見守りながら、そっと背中を押す
→「よくここまで頑張ったね」「次はこの単元をやってみようか」と、日々の努力を認めつつ、前に進む力を与えていきます。 - つまずいた時は、一緒に立ち止まり、立ち上がる
→ うまくいかない時こそ、「大丈夫、次はどうする?」と共に考える姿勢が、自立心を育てる大きな土台になります。
自立とは、孤独に黙々と頑張ることではなく、
「必要なときに支えを受けながら、自分の足で前に進める力」です。
生徒のそばを走りながら、時には先を照らし、時には一緒に立ち止まりながら、
その“自分で進む力”を育てることができるサポーターが必要になります。
もちろん、塾を頼ることも一つの考えです。
ただ、まずは家庭で保護者が子供の頑張りをみて、声がけをすることで、子供はまた頑張ります。
それでも、やはり厳しい。と感じた場合にはじめて塾を検討していただければと思います。
自立学習が身につくとどんな変化が起こるのか?
自立学習が身についた生徒たちは、目に見えて変わっていきます。
最初は「どう勉強すればいいかわからない」と不安げだった子も、少しずつ自分の力で考え、動けるようになっていくのです。
■ 自立学習がもたらす3つの“変化”
① 勉強への“主体性”が生まれる
「やらされている」勉強から、「自分でやる」勉強へ。
自分で立てた目標に向かって取り組むようになると、学習への姿勢がガラッと変わります。
時間の使い方にも工夫が見られ、「今日はこの時間に英語をやろう」と自分で考える力が育ちます。
② わからないことに“立ち向かう力”がつく
教えてもらう前に「まずは自分でやってみる」姿勢が身につくと、問題に対する粘り強さが出てきます。
解けなかった問題を「どうしてできなかったのか」と振り返り、次に活かす力がぐんと伸びます。
③ 成績だけでなく“自信”も伸びる
少しずつでも「自分でできた」という成功体験を積み重ねることで、自然と表情が明るくなり、前向きになります。
「やればできるんだ」という実感は、勉強に限らず日常生活や将来への姿勢にも良い影響を与えます。
登米市のある中学生との出会い「自立学習に切り替えて成績が上がった」
彼と出会ったのは、中学2年生の冬。
登米市内の中学校に通う男の子で、塾に面談にやってきたときは、少しうつむきがちで、目を合わせるのも苦手な様子でした。
お母さまは開口一番、「うちの子、○○という塾に通っていて、勉強してるはずなんですが全然成績が上がらなくて…」とおっしゃいました。
話を聞くと、塾や学校の授業はきちんと受けているけれど、家では何をどうやればいいか分からず、ただノートを眺めているだけのような状態。
テスト勉強も、誰かに言われないと始められない。
わからないところは放置してしまう。
そんな“受け身”の学習スタイルが続いていたのです。
「一緒に計画を立てる」と決めた日から
私は彼に言いました。
「じゃあ、一緒に“今日やること”を決めていこう。全部一気にじゃなくて、小さくていいから。」
最初に立てた計画は、
- 数学のワークを1日1ページ
- 英語の単語を1日5個だけ覚えるたったそれだけ。
でも、その「できそうなことを一緒に決める」ことが、彼のやる気の火種になりました。
やるべきことが明確になることで、彼の中で「今日もやってみよう」という気持ちが少しずつ芽生えたのです。
少しずつ変わり始めた生徒の表情と成績
通塾して1ヶ月が経った頃、彼のノートが変わり始めました。
空欄だった問題に自分なりの考えを書き込み、解けなかった問題には「もう一回」とメモが。
そして迎えた学年末テスト。
数学が22点アップ、英語が28点アップ。
「今までで一番、自分で頑張ったって思えた」と照れながら話す彼の表情は、すっかり前向きになっていました。
自立学習とは、一人で完璧にやることではありません。
「一緒に走る存在」がいてこそ、子どもたちは自分の足で進み始めるのです。
これからも、登米の生徒たち一人ひとりの「やる気の芽」に寄り添いながら、日々精進いたします(^^)/
改めて、学ぶ力を育てていきたいと強く感じた出来事でした。

