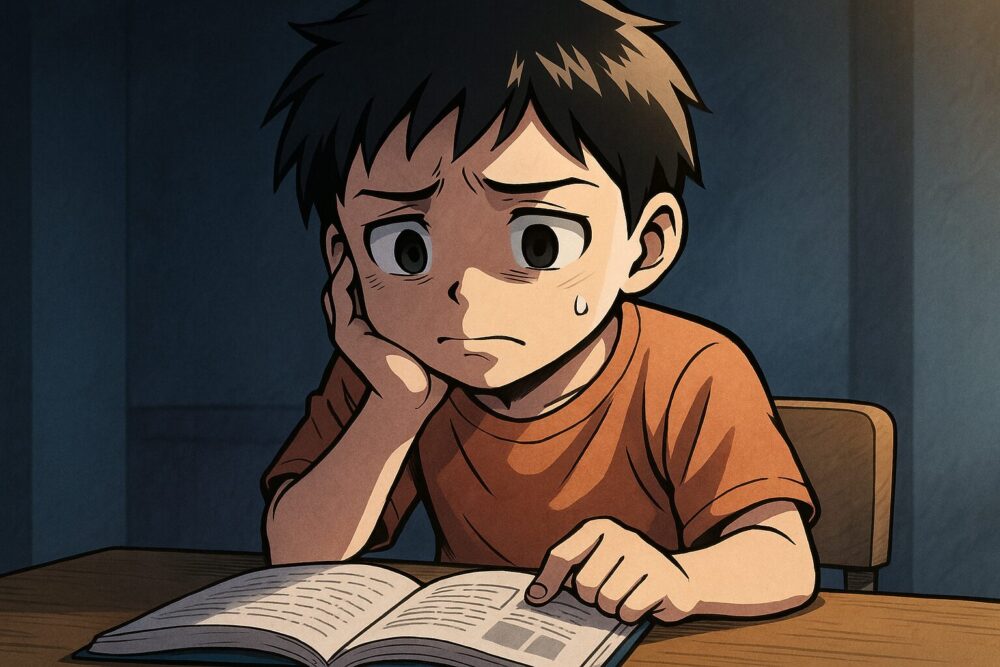小学生の勉強についていけない…親が今できるサポートとは?

ちゃんと勉強しているの?



またそれか・・・。



親は子供のことを気になります。子供はほっといてほしい。ん~なんとも難しい問題じゃな。



本日は小学生の拓海くんとその母さん美咲さんのお話をしてみようかの~。
とある日。
「お母さん、今日の授業、よくわからなかった」
夕方の食卓でそうつぶやいたのは、登米市内にある小学校に通う小学3年生の拓海くんです。
元気で明るく、友達も多い子ですが、最近どうも様子がおかしいのです。宿題の手が止まることが増え、プリントには空欄が目立つようになってきました。
先生からは「大きな問題はないですよ」と言われていましたが、母親の美咲さんは心のどこかで不安を感じていました。
ある日、美咲さんは思い切って拓海くんと一緒に算数の復習をしてみました。
すると、九九はスラスラ言えるのに、文章問題に入ったとたんに手が止まってしまいました。「どうしたの?」と聞いても、「うーん…なんかわかんない」と小さな声。
今回は、そんな拓海くんの姿を通して、小学生が勉強についていけなくなる理由と、親が家庭でできるサポートについて考えていきたいと思います。
小学生は特に見えにくい「勉強についていけない」のサイン
拓海くんは学校では大人しく、授業中に積極的に手を挙げるタイプではありませんでした。
先生から特に注意されることもなく、成績も中の下あたりをうろうろしていたため、家庭でも「まあ大丈夫だろう」と見過ごされがちでした。
けれど、美咲さんがふとした拍子に気づいたのは、学校の宿題をしているときの彼の表情でした。
問題にじっと向かってはいるのに、鉛筆が動かない。
教科書を開いても、読み返すばかりで進まない。そんな姿に、「もしかして、ちゃんと理解できていないのかも」と不安が芽生えました。
登米市の小学生が勉強についていけなくなる主な原因
拓海くんのように、見た目には目立たなくても、実は授業についていけていないという子どもは少なくありません。
一つ目の原因は、基礎の理解があいまいなまま進んでしまっていること
たとえば九九を覚えていても、場面が変わると使い方がわからなくなってしまいます。
これは暗記と理解の間にある大きな壁です。拓海くんも、計算はできても「なぜそうなるのか」という部分でつまずいていました。
二つ目は、家庭での学習習慣の欠如です。
放課後は友達と遊ぶのが楽しみで、家に帰ればテレビやゲームの時間。
宿題をするのは寝る前の数分だけ、という日もありました。登米市のように自然が豊かで、のびのびと育つ環境だからこそ、勉強の習慣づけは家庭の中で意識して作っていく必要があります。
三つ目は、「わかったつもり」で終わってしまっていること
授業で先生の話を聞いて「なんとなく分かった」と思っていても、実際に問題を解くと手が止まってしまいます。
これはアウトプット不足の典型的なパターンです。拓海くんも、教科書を読むと理解した気になるのですが、練習問題ではつまずいてしまっていました。
親のサポートのつもりが子供の勉強の逆効果に?
美咲さんは、拓海くんに「もっと勉強しないとダメじゃない」とつい言ってしまいました。すると、彼はムッとした表情で黙り込んでしまいました。
「なんでやらないの?」と問い詰めれば詰めるほど、息子との距離が広がるような気がしたそうです。
焦る気持ちを抑えて、次の日からは声かけの仕方を変えることにしました。
「一緒にちょっとだけやってみようか」と、拓海くんが苦手にしていた問題を、ゲームのようにして一緒に考えるようにしたのです。
また、できるだけ教えすぎないように気をつけました。
最初は歯がゆい気持ちもありましたが、「なんでそう思ったの?」と問い返すことで、拓海くんの中にある考えのプロセスを引き出すようにしたのです。
そして何よりも、他の子と比較しないことです。
「○○くんはもうここまで終わってるらしいよ」といった何気ない一言が、拓海くんにとっては重たいプレッシャーでした。今は「昨日より自分がちょっとできたか」を一緒に喜ぶようにしています。
子供の「できた!」の積み重ねが自信になります
ある日のこと、美咲さんが用意した計算プリントを、拓海くんが自分から机に向かってやり始めました。「これ、昨日より早くできたよ!」と笑顔を見せました。
その一言に、美咲さんは心の中でそっとガッツポーズをしました。
「できた」「わかった」の感覚を味わうことで、子どもは勉強への抵抗感を少しずつ減らしていきます。
1日5分のプリントでも、たとえ一問でも、それが子どもにとっての自信の種になるのです。
また、苦手な単元に戻ることを怖がらせないことも大切です。拓海くんが1年生の漢字でつまずいていることに気づいたとき、美咲さんは「今やれば、もっと楽になるかもね」と声をかけて一緒に復習しました。
その結果、新しい単元でも漢字を読めることが増え、授業中に自信を持って発言するようになったといいます。
まとめ:勉強ができないことに焦らなくていい、でも目をそらさないで
勉強が遅れていると気づいたとき、親としてはつい焦ってしまいます。
でも、大切なのは「何をやらせるか」よりも、「どんな気持ちで関わるか」だと美咲さんは気づきました。拓海くんが安心して「わからない」と言える環境をつくることで、少しずつ勉強に向き合う姿勢が育っていったのです。
小学生の勉強の遅れは、今なら取り戻せます。今、気づけたことこそが、最初の一歩です。拓海くんのような子どもたちが、もう一度「勉強ってちょっと楽しいかも」と思える日が増えていくことを願っています。